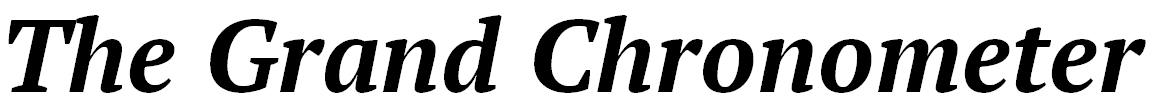高級機械式時計の代名詞であるロレックス。一生モノとして迎え入れる方が多いからこそ、「高価な時計を誤って壊してしまわないか」という不安は尽きません。中でも、時計が止まったときにリューズを回して動力を与える「手巻き作業」は、多くの方が最も神経を使う瞬間ではないでしょうか。
インターネットでは、「ゼンマイは巻きすぎると切れる」「巻きすぎは故障の原因になる」といった情報が飛び交っていますが、それはロレックスの自動巻きモデルにも当てはまるのでしょうか。
ご安心ください。結論から申し上げると、現在流通しているほとんどのロレックス自動巻きモデルは、構造上、ゼンマイを巻きすぎる心配はほぼありません。
しかし、これは「どのように扱っても大丈夫」という意味ではありません。ロレックスの繊細な内部機構を理解せず、誤った方法で過度な負荷をかけ続ければ、部品の摩耗や損傷を早めることにつながります。
この専門ガイドでは、あなたが抱える「ロレックスのゼンマイ巻きすぎ問題」の不安を完全に解消します。なぜロレックスの自動巻きは巻きすぎない設計になっているのか、その驚くべき技術から、止まった時の正しい巻き上げ回数、そして時計を長持ちさせるためのメンテナンス知識まで、2025年9月現在の最新情報に基づき、深く掘り下げて解説します。
この記事を読み終える頃には、ロレックスという精密機械に対する理解が深まり、購入への迷いが消え、自信をもって愛機を扱うことができるでしょう。ぜひ、安心と愛着を持ってロレックスを扱うための最初の一歩として、読み進めてください。
- 自動巻きロレックスは巻きすぎない設計であること
- 巻きすぎ防止機構の具体的な仕組みと役割
- 時計が止まった時の正しい巻き上げ回数の目安
- ゼンマイ切れなど故障の真の原因と対処法
ロレックスの自動巻きは「ゼンマイを巻きすぎない」設計になっている

ロレックスの自動巻き(パーペチュアル)ムーブメントは、長年の技術革新により非常に洗練された構造を持っています。この技術こそが、オーナーの皆様が抱く「巻きすぎによる故障」の不安を根本から解消しています。
自動巻き時計において、ゼンマイが動力源となることに変わりはありませんが、手巻き時計とは決定的に異なるメカニズムを採用しています。この仕組みを理解すれば、リューズを回す際も、腕に着けて生活する際も、安心してロレックスを扱うことができるでしょう。
安心の技術:ロレックスが誇る巻きすぎ防止「スリップ機構」
ロレックスの自動巻きモデルには、ゼンマイを自動で巻き上げすぎるのを防ぐための特殊な機構が組み込まれています。これは一般的に「スリップ機構(スリッピング・クラッチ)」と呼ばれるものです。
ゼンマイは、ムーブメント内の「香箱(こうばこ)」という円筒形のケースに収められています。ゼンマイが完全に巻き上がって満タンの状態になると、さらに動力が加わっても、ゼンマイの端が香箱内壁に設けられた特別な摩擦装置から滑る(スリップする)ように設計されています。
このスリップ機構の役割は、例えるなら自動車のクラッチのようなものです。動力が満タンになった時点でクラッチが切れることで、それ以上の無理な力がゼンマイや歯車にかかるのを防いでいるのです。
つまり、自動巻きのロレックスを腕に着けている限り、日常生活でどれだけ活発に動いても、内部のローター(自動巻き機構)が勝手にゼンマイを巻きすぎて切ってしまう心配はありません。この堅牢かつ巧妙な仕組みこそが、ロレックスの信頼性を支える重要な要素の一つです。
手巻き時計との決定的な違い:「巻き止まり」の有無
現代のロレックスの自動巻きモデルと異なり、手巻き時計(手巻きモデル)にはこのスリップ機構がありません。そのため、「ゼンマイ時計は巻きすぎに注意すべきですか?」という問いへの回答は、手巻き時計に関しては「イエス」となります。
手巻き時計のゼンマイには明確な「巻き止まり」が存在します。これは、ゼンマイが完全に巻かれきった時に、リューズが回らなくなる、または非常に重くなる感覚として指先に伝わるものです。
| 手巻き時計 |
| 巻き止まりの感覚を無視して無理に力を加え続けると、ゼンマイの端が切れる「ゼンマイ切れ」を引き起こし、ムーブメントに致命的なダメージを与える可能性があります。 |
| ロレックスの自動巻き |
| ゼンマイが満巻に近づくと自動的にスリップ機構が作動するため、リューズを回しても「巻き止まり」のような完全な抵抗がなく、理論上はいつまでも回り続けます。 |
ロレックスにおいても、過去のモデルや、ごく一部の特殊な機構を持つモデルは手巻き式である場合があります。それらの時計を取り扱う際は、現代の自動巻きモデルとは異なる注意が必要ですが、現行のほとんどのオイスター パーペチュアル シリーズをお持ちであれば、この「巻きすぎ」の不安は解消できるでしょう。
【実践編】ロレックスの「正しい巻き方」と「巻き上げ回数」のすべて

前の章で、ロレックスの自動巻きモデルは構造的に巻きすぎる心配がないことをご理解いただけたかと思います。しかし、時計が止まったときや、長期間使用しなかった後に再び使用する際には、リューズを手動で巻く「追い巻き」が必要です。
このセクションでは、「リューズで何回巻けばいいのか」「毎日巻いてもいいのか」といった具体的な疑問に、最新の知見に基づいてお答えします。
止まったら何回巻くべき?リューズ手巻きの回数目安とコツ
ロレックスの自動巻きは、腕に着けて生活することでローターが回転し、自動的にゼンマイが巻き上げられます。しかし、数日間着用しなかった場合、時計は動力を使い果たして止まってしまいます。この状態から再び時計を動かすためには、リューズを使って手動でゼンマイを巻き上げる必要があります。
リューズによる手巻き回数の目安
ロレックスのムーブメントに関する公式見解は非常に慎重ですが、長年の専門家の知見や修理現場のデータに基づくと、止まった状態から時計をしっかりと稼働させるために必要な巻き上げ回数の目安は以下の通りです。
| 状況 | 巻き上げ回数の目安 |
| 完全に停止した状態から動かすとき | 30回~40回 |
この回数を巻くことで、ゼンマイはほぼ満巻に近い状態となり、ムーブメントは本来の精度で安定して動作し始めます。「ロレックスのゼンマイは何回巻いたらいいですか?」という疑問に対する、最も実用的な答えと言えるでしょう。
【重要】巻きすぎの具体的な感覚(スリップ音)
「40回以上巻いても大丈夫?」と不安に感じる方もいるかもしれません。前述のスリップ機構があるため、リューズは回し続けることができますが、満巻に近い状態になると、リューズを回す指の感触が以下のように変化します。
- 通常の状態
- カチカチとゼンマイが巻き上がる確かな手応えがあります。
- スリップ開始
- 30~40回を超え、満巻に近づくと、リューズの感触がわずかに軽くなる、あるいは「カチカチ」という音から「シャーッ」という極微かな摩擦音(スリップ音)に変わることがあります。
この変化を感じたら、それがゼンマイが満巻になったサインです。それ以上、無理に力を込めて回し続ける必要はありません。巻きすぎを防ぐ機能があっても、不必要にスリップを繰り返すことは、機構の摩耗を早める可能性があるからです。
「ロレックス ゼンマイ 毎日」巻いても大丈夫?頻度の考え方
自動巻きのロレックスは、腕に着けているだけで自動的にゼンマイが巻かれるため、基本的に毎日手巻きする必要はありません。
「ロレックス ゼンマイ 毎日」と検索する方は、精度を保つために習慣的に巻き足すべきかと考えているかもしれませんが、これはむしろ避けるべきです。
毎日手巻きを繰り返すことは、ムーブメント内の手巻き機構(巻き真やリューズチューブ)に不必要な摩擦と負荷をかけることになります。自動巻き時計は、本来、腕の動きで巻かれることを前提として設計されています。
- 止まってしまった時
- 上記目安(30〜40回)で巻き上げる。
- 週末だけ着用するなど着用頻度が低い時
- 完全に止まる前に、補助として少しだけ巻き足す。
長期間着用しない場合は、無理に毎日巻くよりも、次に着用する際に改めて手巻きで始動させる方が、時計全体への負担は少なくなります。
巻き上げ補助としての「ロレックスの自動巻きを振る」は推奨されない
「ロレックス 自動巻き 振る」という検索も多く見られますが、これも避けるべき対処法です。
時計が止まってしまった時、つい「振って」ローターを強制的に回し、動力を得ようとする方がいます。しかし、強い力で振る行為は、ムーブメント内部のローターの軸や、繊細なテンプなどの部品に大きな衝撃と負荷をかけることになります。
特に、ロレックスの現行ムーブメント(Cal. 3235など)は、高い耐衝撃性を誇るものの、故意に大きな力を加えることは推奨されません。
時計が停止した場合は、必ずリューズ(手巻き)で優しく、ゆっくりと動力を与えるようにしてください。リューズによる巻き上げは、最もムーブメントに優しく、確実に動作をスタートさせるための正式な方法です。
ロレックスが「巻きすぎ以外」で止まる真の原因とメンテナンス

- 「ロレックスの自動巻きがすぐ止まる」原因の9割は巻き上げ不足とパワーリザーブ
- 巻きすぎではない?「ゼンマイ切れ」の具体的な症状と修理費用
- よくある質問(FAQ)
- ロレックスのゼンマイ巻きすぎに対する最終的な総括と知識の確認
- 【関連情報】ロレックスが止まるもう一つの原因「磁気帯び」を知っていますか?
巻きすぎの不安が解消されたところで、次に考えたいのが「ロレックスの自動巻きがすぐ止まる」という問題です。前述した通り、構造上「巻きすぎ」が原因で時計が壊れて止まることは稀です。多くの場合、時計が止まる原因は他にあります。
ここでは、時計が停止する主な原因と、それを防ぐためのメンテナンスの重要性について解説します。
「ロレックスの自動巻きがすぐ止まる」原因の9割は巻き上げ不足とパワーリザーブ
時計が止まる原因として最も多いのは、やはり「動力不足」です。
ロレックスの現行自動巻きムーブメントは、完全に巻き上がった状態から静止させた場合、およそ70時間(約3日弱)のパワーリザーブ(駆動持続時間)を持ちます。これは優れた持続力ですが、以下のようなライフスタイルでは動力が不足し、時計が止まることがあります。
| 週末の休止 |
| 金曜日の夜に外して月曜日の朝に着ける場合、ちょうど70時間を超えて止まってしまう。 |
| デスクワーク中心 |
| 腕の動きが少ないとローターの回転が足りず、手巻きによる補助なしでは満巻まで巻き上がらない。 |
「ロレックスの自動巻きは何日で止まる?」という疑問への答えは「約3日」ですが、この時間を把握し、定期的に時計の状態をチェックすることが重要です。時計が止まっていない状態でも、パワーリザーブが低下すると精度が不安定になることがあるため、日々の着用時間を確保するか、適切な手巻き補助を心がけてください。
巻きすぎではない?「ゼンマイ切れ」の具体的な症状と修理費用
時計が止まった際、最も心配されるのが「ゼンマイ切れ」でしょう。これは、ゼンマイが途中で破断し、時計が完全に動力を失う故障です。
しかし、ロレックスの自動巻きモデルのゼンマイ切れの原因は、巻きすぎにあることはほとんどなく、多くは以下の二点によるものです。
| 1. 金属疲労 |
| ゼンマイは弾力性を保つために常に伸縮を繰り返しており、長期間の使用(通常は5~10年程度)により徐々に劣化します。 |
| 2. 強い衝撃 |
| 落下などによる瞬間的な強い衝撃により、ゼンマイが耐えきれずに切れてしまうことがあります。 |
ゼンマイ切れの症状
ゼンマイが切れると、以下のような症状が現れます。
- リューズを回しても、カチカチという巻き上げの手ごたえが一切ない、またはリューズが空回りする。
- 時計が完全に停止し、振っても秒針が一瞬動いてすぐ戻る(ローターが回っているだけで動力が伝わらない)。
ゼンマイ交換・修理費用(2025年9月現在)
ゼンマイが切れた場合、ムーブメントの精密な点検と部品交換が必要となるため、時計のオーバーホール(分解掃除)が必須となります。そのため、ロレックスのゼンマイ交換費用としては、このオーバーホール費用を目安に考える必要があります。
| サービス依頼先 | 基本技術料(目安) |
| 正規サービス | 77,000円~110,000円(税込) |
| 優良な民間修理店 | 38,500円~50,000円(税込) |
特に正規サービスでは、ゼンマイや他の摩耗部品が予防的に交換されるため、最終的な費用は高額になる傾向があります。この高額な修理費用を避けるためにも、ロレックスが推奨する5~10年ごとの定期的なオーバーホールは、時計の寿命を延ばすために不可欠な大切なメンテナンスと言えるでしょう。
よくある質問(FAQ)
- ロレックスの自動巻きは、本当に巻きすぎても大丈夫ですか?
-
はい、構造上、巻きすぎる心配は基本的にありません。
現行のロレックス自動巻きモデルには「スリップ機構」が搭載されています。ゼンマイが満巻になると自動的にクラッチが滑る(スリップする)ため、それ以上無理な力がかかるのを防ぎ、ゼンマイ切れを防いでいます。ただし、不要な巻き上げを繰り返すと部品の摩耗を早める可能性があるため、適切な回数にとどめるのが理想です。
- 時計が止まったら、リューズは何回巻けば動きますか?
-
完全に止まった状態から時計を始動させる場合、リューズを30回から40回を目安に、ゆっくりと回してください。
この回数でゼンマイはほぼ満巻に近い状態となり、時計が安定して動作し始めます。40回を超えても回り続けますが、感触が軽くなったら巻き上げ完了のサインと考え、無理に力を加えないようにしましょう。
- ロレックスを毎日手動で巻いたほうが精度が上がりますか?
-
必ずしも毎日巻く必要はありません。
ロレックスは腕に着けているだけで自動的にゼンマイが巻かれる設計です。毎日手巻きすると、手巻き機構に不必要な摩擦をかけることになり、部品の寿命を早める可能性があります。頻繁に着用する場合は、完全に止まったときや、数日ぶりに着用する前の補助として巻く程度で十分です。
- ロレックスが止まる主な原因は何ですか?
-
「巻きすぎ」が原因で止まることは稀です。主な原因は以下の3つです。
- 巻き上げ不足:特にデスクワークなどで腕の動きが少ない場合、ゼンマイが十分に巻かれない。
- パワーリザーブ切れ:現行モデルの駆動持続時間は約70時間(約3日弱)のため、数日着用しないと止まる。
- 磁気帯び:スマートフォンやPCなどの強い磁気にさらされると、精度が乱れたり、時計が止まったりすることがある。
- ゼンマイ切れの修理費用はいくらくらいかかりますか?
-
ゼンマイが切れた場合、ムーブメント全体の点検・整備が必要となるため、オーバーホール(分解掃除)が必須となります。
正規店(日本ロレックス)での基本技術料はモデルによって異なりますが、およそ7万円〜11万円(税込)が目安です。これにゼンマイなどの部品交換費用が加算されるため、修理費用は高額になることを念頭に置きましょう。
ロレックスのゼンマイ巻きすぎに対する最終的な総括と知識の確認
- 現行のロレックス自動巻きは構造上、巻きすぎる心配がない
- 巻きすぎを防ぐ「スリップ機構」が満巻時に自動で機能する
- スリップ機構は、ゼンマイが切れないように動力を逃がす役割を持つ
- 手巻き時計とは異なり、自動巻きには明確な巻き止まりがない
- 時計が完全に止まったら、リューズで30回〜40回を目安に巻く
- 巻き上げ時にわずかに感触が軽くなったら、満巻のサインである
- 満巻になったら、それ以上無理に力を加えて巻き続けない
- 自動巻きは着用していれば動力が得られるため、毎日巻く必要はない
- 頻繁な手巻きは、かえって手巻き機構の摩耗を早める可能性がある
- 時計が停止しても、振って動かす行為はローター軸に負荷をかけるため避ける
- 時計がすぐに止まる最大の原因は、巻き上げ不足とパワーリザーブ切れである
- 現行モデルのパワーリザーブは約70時間(約3日弱)が目安である
- ゼンマイ切れの主な原因は、金属疲労や強い衝撃である
- ゼンマイ切れを含む修理には、オーバーホールが必須となり高額になる
- ロレックスの寿命を延ばすために、5〜10年ごとの定期的なオーバーホールを推奨する
この記事を通じて、ロレックスの自動巻きモデルにおける「ゼンマイの巻きすぎ」に対する不安は、構造的な技術によってほとんどが解消されていることをご理解いただけたかと思います。
ロレックスは、技術の粋を集めたスリップ機構により、過剰な巻き上げを防ぐ、非常に堅牢な設計がなされています。しかし、この堅牢さは誤った使い方や不十分なメンテナンスを許容するものではありません。
- 知識をもって扱うこと: 巻きすぎ防止機能に頼りきるのではなく、リューズを回す際は優しく、目安回数で十分と知ること。
- 優しく扱うこと: 止まった時は振らず、リューズで巻き上げることを徹底すること。
- 定期的にケアすること: ゼンマイの金属疲労や油切れを防ぐため、推奨される頻度でのオーバーホールを欠かさないこと。
これらの正しい知識と、ご自身の愛機に対する愛着をもって接することで、ロレックスは世代を超えて正確に時を刻み続ける、生涯のパートナーとなるでしょう。
ロレックス公式サイトhttps://www.rolex.com/ja/watches
【関連情報】ロレックスが止まるもう一つの原因「磁気帯び」を知っていますか?
時計が頻繁に止まったり、急に時間が大幅に進んだり遅れたりする場合、ゼンマイ切れや動力不足の他に、現代生活特有の大きな原因が潜んでいます。それは、スマートフォンやPC、家電などから発生する磁気を時計が帯びてしまう「磁気帯び(帯磁)」です。
巻き上げ不足の次に多い故障原因とも言われる「磁気帯び」について、その症状の見分け方や、ご自宅でできる簡単な予防・対処法を別の記事で徹底解説しています。もし、あなたのロレックスが不調を感じているようでしたら、ぜひこちらもご参照ください。

日常生活に溢れる磁気は、愛機を脅かす身近なリスクです。磁気帯びについて、その症状の見分け方や、ご自宅でできる簡単な予防・対処法をより深く知りたい方は、他ブランドの事例ですが、時計が磁気から受ける影響の原理と対策が詳細に解説されている下記の記事もぜひご参照ください。

次回の記事では、ロレックスに特化し、ミルガウスやブルー パラクロム・ヘアスプリングなどの独自技術に焦点を当てて詳しく解説する予定です。